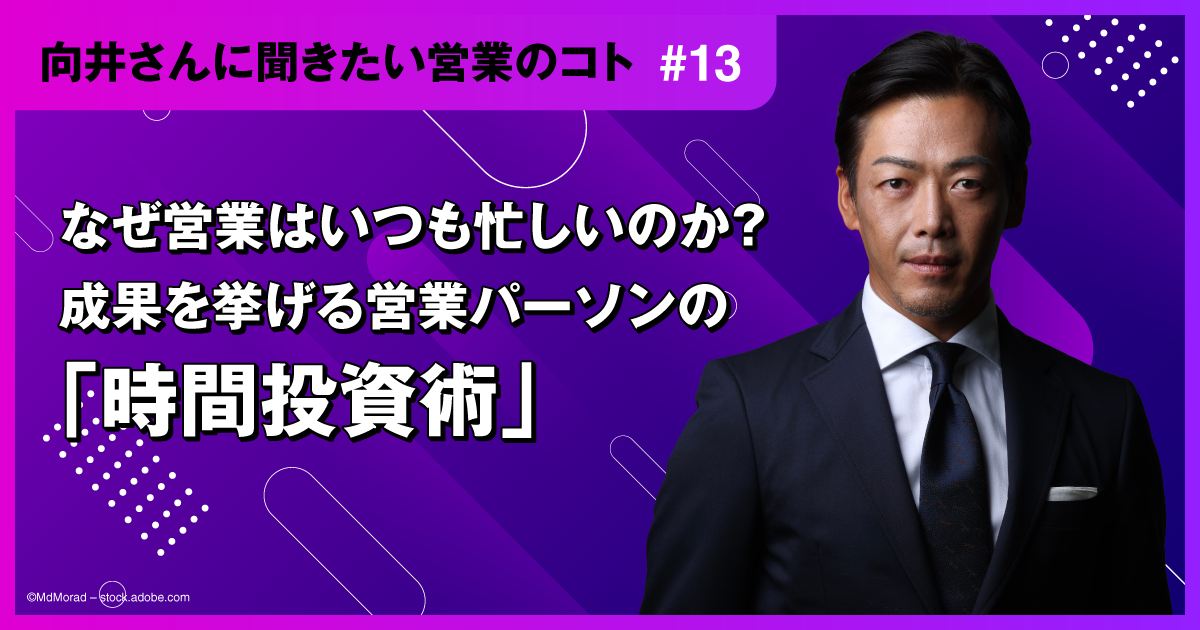現代営業を襲う、「忙しさ」の正体とは
デジタルデバイスとコンテンツの変化は、私が社会人になった2000年代初頭から比べると劇的です。テクノロジーの進化により、普段の仕事は段違いに便利になったはずなのに、日本の生産性やGDPは横ばい。この矛盾を、私たちは真正面から受け止めるべきでしょう。
「慢性的な忙しさ」の原因は個人と組織、双方にあると私は考えています。
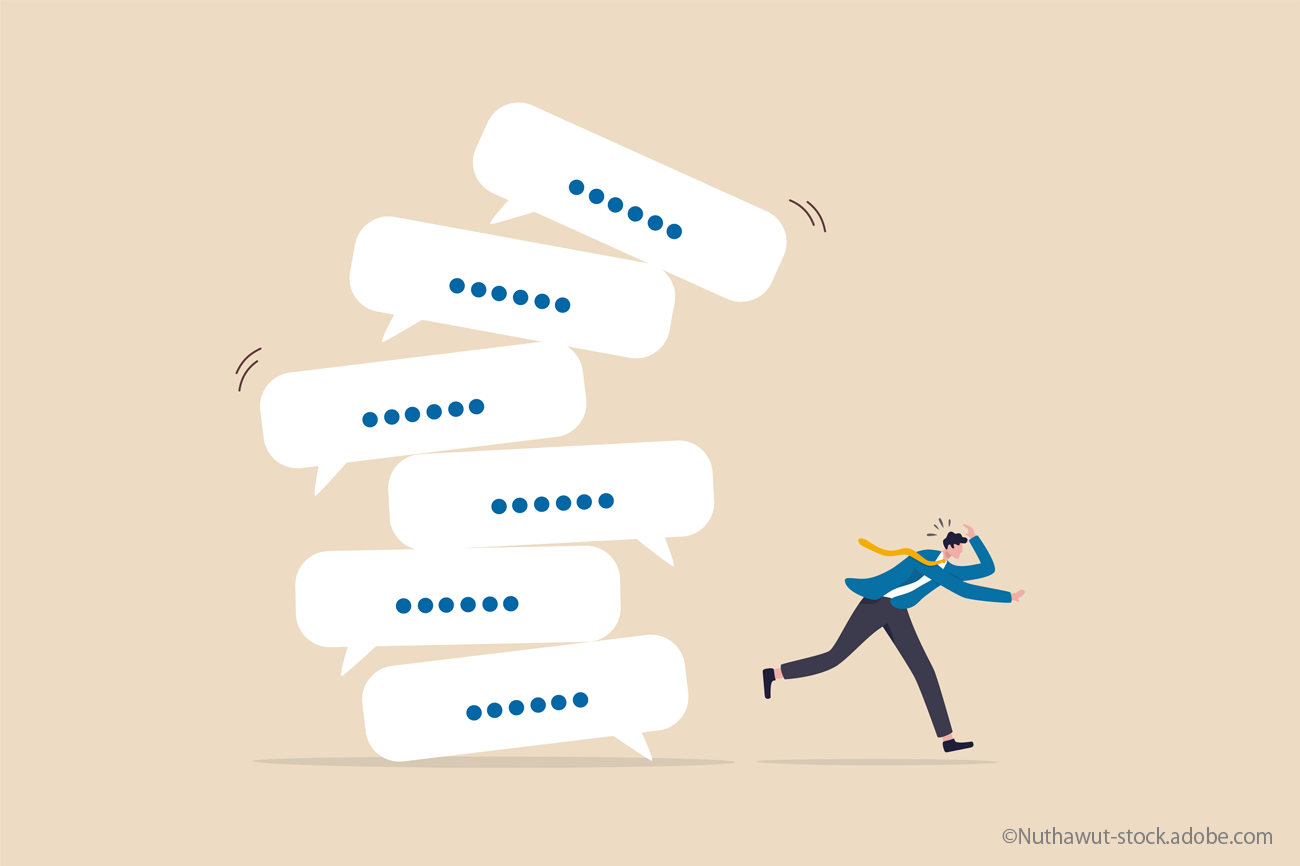
まず、便利になりすぎた結果、私たちは「常時接続」の弊害に囚われています。手元のデバイスから来る通知こそが、忙しさの最大の原因のひとつです。
非同期ツールでの“即レス”要求という矛盾
本来、メールやチャットは、相手の都合を考えなくて良い非同期コミュニケーションツールのはず。にもかかわらず、とくにチャットでは、まるで電話のように同期型(リアルタイム)のレスポンスが暗黙の了解になってしまっています。「Slackにスタンプがない……」「このLINEは既読無視だろうか?」といったプレッシャーが蔓延し、「即座に反応しないと仕事が滞る」という幻想にも縛られています。
集中力を破壊する「細切れトランザクション」
この即レス要求の雰囲気が、「細切れのリアルタイム対応」を求め合う状況を生み出しています。通知が鳴るたびに集中力が切れ、タスクの切り替えコストが発生します。結果、多くの営業パーソンがチャットに振り回され、もっとも重要な「考える時間」を失っているのです。
フロー型ツールによる、TODO管理の難しさ
また、チャット系ツール(Slack/LINEなど)は、流れてきた情報がすぐに埋もれるフロー型です。来たタイミングで処理を行わないと見失いやすく、後回しが難しい。「TODO管理がうまくいかない」と感じる原因は、メールなどと比べてチャットコミュニケーションでは未処理のTODOのストックが難しいからでしょう。
「優秀な人ほどボールを持たない」は本当?
また、世間でよく言われている「優秀な人ほどボールを持たない(即判断し、即レスポンスする)」という言説には、注意が必要です。現場レベルの営業パーソンにとっては、むしろ不要な焦燥感を生む原因になりかねないからです。
もちろん、一定の役職以上になれば、権限と知見があるため、即座に判断・回答することが可能です。しかし、一社員である営業パーソンが、自分の判断だけで進められるタスクはごくわずかです。
とくに顧客への提案は、社内の技術部門や法務、さらには社外の協力会社との綿密な調整が必須です。つまり、「ボールを持たざるを得ない」のが営業だとも言え得ます。
それにもかかわらず、「即レス」が求められる風潮の中で、調整によってタスクが停滞してしまう自分を、「能力が低いのではないか」「環境が悪いのではないか」と追い詰めてしまう人が増えています。
昔も今も、営業の忙しさの根源は「調整の多さ」にあります。そこに、非現実的な「即レス文化」が加わることで、精神的な負荷が格段に上がっているのが今の現場のリアルなのではないでしょうか。